魔法の言葉は魔法使いだけのものではありません
何でも生まれつき?
世の中には背の高い人もいますし、背の低い人もいます。昔は牛乳をたくさん飲めば背が高くなると言われて、1Lのパックをがぶ飲みする人もいましたが、一日に摂取できるカルシウムの量には限界があるでしょうから、努力したほどに効果は期待できないというのが現実でしょう。一方、世の中には太った人とそうでない人がいて、個人差はありますがこれは努力である程度は改善できます。私もこれまで様々なダイエットにチャレンジして、炭水化物の摂取を極力抑えることで、10㎏以上体重を落とすのに成功したことがあります。
運動もそうで、元々足の速い人もいれば、元々足の遅い人もいます。そして、元々足は速くて努力してさらに早くなる人もいれば、元々足は遅いけど努力して早くなる人もいます。前者は生まれ持った能力であり、後者は後天的に努力して獲得したものです。
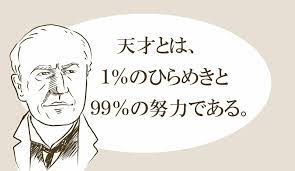
では宅建試験といった勉強についてはどうでしょう?私は正直それほど「学校の勉強」が得意な方ではありません。特に苦手なのが暗記を必要とする分野で、歴史の年号暗記などは全滅でした。一方で数学など理系科目については、公式をいくつか覚えておけばパズルのように組み合わせることで答えを導くことができるので比較的成績は良い方でした。
当時学校で成績の良い同級生を見ていて、いつも「どうせあいつは生まれつき記憶力が良いに違いない」と嫉妬していましたが、それは大きな間違いで、多くの場合彼らは努力によって記憶に長けていたのであって、誰もが才能に恵まれていたわけではないのです。
能力と技術の違い
記憶「力」というのは生まれつき持っている「能力」で、能力のある人はそれほど努力しなくても物事を覚えることができます。生まれつき走るのが速い人と同じです。一方で記憶「術」というのは技術なので、多くの人が努力することにより習得できます。しかもそうした術の多くは、技術を正しく習得することができれば、誰もが物事を覚えられるように設計されています。
代表的な記憶術の一つに「語呂合わせ」があります。私は記憶術の専門家ではないので、あまり深くは触れませんが、覚えにくい言葉などを関連する別の覚えやすい言葉に置き換えることで暗記します。暗記したい複数の言葉を、絵や写真のようなイメージに置き換えることで記憶を定着させるという暗記方法もあります。どのやり方も、技術を習得することでかなり高い確率で記憶を定着することが可能です。ただ、正直語呂合わせはあまり宅建試験の勉強には使えませんが、(そういう本を買ってしまって言うのもなんですが)、それ以外で使える記憶術も中にはあります。

避けては通れない道
これは宅建試験のどの教科書を開いても必ず出てくる、忌々しい用途地域の表です。多くの教科書には「この表は重要なので必ず覚えてください」みたいなことが書いてあると思うのですが、「言うは易く行うは難し」で、そんな簡単に覚えることができれば世話ないです。

私も何度となく表をそのまま暗記しようとしましたが、本当に何度も挫折しました。だって、そもそも暗記が苦手なんですから。そこで、適当な語呂合わせでもないものかとネットを検索していて見つけたのが、これから紹介する「魔法の言葉、『ほじとろし』」です。
魔法の言葉を唱えると…
用途地域の分類は表を見ていただく通り、13の地域名と各地域において許可されている建築物の用途が表記されています。宅建試験では
建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
(宅建過去問2002年 問-20)
肢:第一種低層住宅専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
のように出題されます。はっきり言って、覚えてさえいれば誰でも解けますが、覚えていなければどうやっても正答できません。宅建試験では毎年必ず出題される問題で、落としたくなければ表を覚えるしかないのです。

いきなり表を丸ごと覚えるのは大変なので、まずは13種類の地域名を全て覚えましょう。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 田園住居地域
「いや、13も覚えられない、無理!」という悲鳴が聞こえてきそうですが、よくよく分析すればそれ程難しくはありません。最初の6地域はそ低層、中高層、その他(住居地域)の3種類でそれぞれに一種、二種があります。覚えにくい人は、実際の街並みがどうなっているか教科書で確認して身近な街の風景を重ねると良いです。これで、覚えるのはあと7つですね。
商業系が三つ(準住居地域は準商業地域みたいなものなので)、工業系が三つで、それぞれ準、およそ、専門みたいな区切りになっています。これで12覚えられましたね。最後の田園住居地域は住居みたいなものと覚えておけば大丈夫です。最初は順番を気にしなくても構いませんが、宅建試験前までには順番も含めて13の用途地域名をしっかり覚えてください。
さてここから本題です。まずは魔法の言葉の核となる「ほじとろし」を覚えてください。意味の無い言葉なので、最初は戸惑うかもしれませんが、呪文のように何度か唱えて覚えましょう。これは何を意味するかというと、ほ=保健所、診療所、じ=住宅、共同住宅、と=図書館、ろ=老人ホーム、し=小学校、中学校、高等学校(小中高)の頭文字をまとめたもので、実は用途地域の1番目である、第一種低層住居専用地域で認められる建築物となっています。
この「ほじとろし」を覚えたら、次は「ほじとろし、てん」と覚えてください。てん=店舗(床面積150㎡以下)のことです。更に「ほじとろし、だびてん」と覚えてください。だ=大学、び=病院、てん=店舗の意味です。そしてこの「ほじとろし、だびてん」は2回繰り返します。
「ほじとろしだびてん」が覚えられたら、「ほじとろしだびてん、ぼほ」を覚えます。ぼ=ボーリング場、ほ=ホテルです。最後に「ほじとろしだびてん、ぼほか(ら)」を覚えます。か(ら)=カラオケです。
ここまで順調に覚えることができれば、ほぼ表の半分は覚えたも同然です。(残りの7地域については自分で魔法の言葉をアレンジしてみてください)
一般的に全く無秩序に並んだ数字や記号をその通りに覚えるのは大変ですが、このように少しずつ増えていく順列は比較的容易に覚えることができます。
「こんなので覚えられるわけがない」と思う方も多いと思いますが、騙されたと思ってこの半分だけでも構いませんから試してみてください。
この宅建試験に特化した記憶術、参考にしたブログはこちらです。

積み重ねが合格に導く
先に引用した宅建試験平成14年の問題ですが、第一種低層住居専用地域で建築できるのは「ほじとろし」なので、し=小学校は建築できて当然、つまりこの肢は誤りであると判断できます。私が宅建試験を受けた令和2年10月の試験問題では、問18でこの用途地域について触れられており、表を覚えていれば少なくとも肢2が誤りであることに容易に気づくことができたはずです。
元々学校の勉強が得意な人は、こんなテクニックを使わなくとも簡単に合格点を取ることができるのかもしれませんが、そうでない、いわゆる「持たざる人」には、「持たざる人」なりのやり方があります。能力が足りなくても「術=技術」を習得することで、能力の足りない部分をカバーするのは十分可能です。そうした努力を一つずつ積み重ねることが、一点一点の積み重ねとなり、重ねた回数分合格点に近づくという事です。

ブログランキング参加中。バナーのクリックよろしくお願いします!
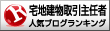
宅地建物取引主任者ランキング
